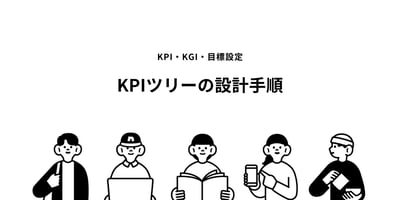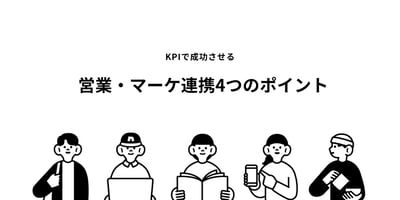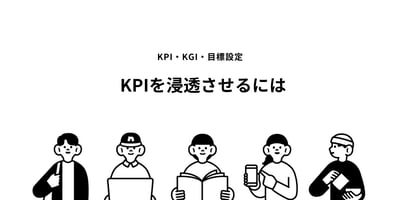今回は、このような課題にお答えします。 そもそもKPI設定の仕方がわからない。 KPI設定をしてなかったので、ちゃんとKPI設定をしたい。 マーケティン部門にも売上目標が課せられてしまった。...
『最高のKPIマネジメント』を参考に、KPIを設定してみました。
こんな方におすすめです
- これからKPI設計する方
- KPIが設計されていない現場の方
- 新規にデジタルマーケティング部門を立ち上げた方
今回は、「最高の結果を出すKPIマネジメント」という書籍をもとに、実際にKPIをつくってみました。
前提内容
今回は、大手広告代理店の子会社が、子会社独自での販売ルートを確立するためのデジタルマーケティング部門のKPIの設計を行いたいと思います。
デジタルマーケティング部門は、設立されて3年経ちます。
毎年の組織変更があり、担当者が1年で変わってきました。
KPIがない・KPIツリーが機能しない原因とは?失敗パターンと対策でも書いたのですが、デジタルマーケティングに精通した責任者・担当者がいないため、KPIが設定されていないという状況です。
KPI設計の前に注意したこと
注意することは下記の4点と書かれています。
- 多すぎる指標
- コントロールできない指標(GDP)
- 遅行指標
- 定期的にみている指標の中にKSFがない
多すぎる指標は、よくあることではないでしょうか。
また、KSFが設定されていない現場も多いです。KSFについては、KSFの設定方法と具体例|KGI・KPIとの連携術を徹底解説にもまとめたので、こちらも参考してください。
KPI設計の準備
1.ゴールとKGIの確認
インバウンドマーケティングの体制を組んでいます。
背景としては、親会社からの案件だけでなく、自社でも案件を獲得できる体制を整えたいということから始まりました。当面のゴールは、インバウンドマーケティングで売り上げを立てる仕組みを構築すること、になります。
次に、KGIですが、売上額になります。立ち上げたばかりなので、まずは売上を立てることが重要な段階です。
ゴール:インバウンドマーケティングで売り上げを立てる仕組みを構築すること
KGI:売上額
営業部門と共有して組み立てる必要があり、スムーズに連携するための4つのポイントも意識して実施しました。
2.現在とのギャップ
今期はすでに10か月も経過しています。
現在は、やっと3,000万円の受注が1件取れるか取れないかという状況なので、大幅に下回っています。
3.プロセスの確認
事業部のビジネスを数式にしてみました。
最もシンプルな数式だと、
売上=受注数×平均単価
になりますが、少し分解して、下記の数式にしました。
売上=商談数×受注率×平均単価
売上を上げる選択肢は、
- 商談数を上げる
- 受注率を上げる
- 平均単価を上げる
となり、そのために何をすればいいか?を考えればよいということになります。
4.絞り込み・KSFの設定
KSFは、コントロールできるかどうか?で判断します。
本書では、定数と変数にわける、となっています。
定数を洗い出し、残ったものが変数で、変数の中からKSFを選ぶという順番です。
KPIの数式を定数と変数にわける
売上=商談数×受注率×平均単価
まずは、それぞれのKPIを上げるために、何ができるのか?できないのか?を洗い出してみました。
商談数を上げるには、その前のプロセスでの数字を上げることが必要です。
商談に至るまでのプロセスを分解すると、リード/MQLを獲得→アポイントを獲得→商談、となります。
オウンドメディアで、リード/MQLを獲得し、インサイドセールスが電話やメールでアポイントを獲得しているため、商談数を上げる施策は打てます。
受注率を上げるには、商談の際にインセンティブを提示したり、提案の質を上げるなどで対応ができます。また、営業だけでなく、コンサルタントの同席なども考えられます。受注率を上げる施策は打てます。
平均単価を上げるには、顧客の予算にゆだねられます。一定の工夫はできますが、コントロールするのは難しそうです。
このように考え、平均単価が定数、あとは変数としました。
売上=商談数(変数)×受注率(変数)×平均単価(定数)
変数をもとに、KSFを決定する
商談数と受注率が変数になります。
これらをさらに分解して、KSFを決定していきます。
商談数は、圧倒的に数が足りません。そのため、受注率を上げても売上への貢献度は低いというのがわかっています。
ということから、商談数を深堀することにしました。
前述のとおり、リード/MQLを獲得→アポイントを獲得→商談と分解できます。
また、ここで、ゴールを確認しておきます。
ゴール:インバウンドマーケティングで売り上げを立てる仕組みを構築すること
仕組みの構築です。
ボトルネックとなっている個所は、MQLからアポイントへの転換です。
アポイント率が低く、アポイント獲得のための活動は、兼務で動いている担当者のリソースの空き状況により左右されています。また、一度電話やメールをして、つながらないと、そのまま放置してしまっている状況です。
ここを改善しないと、商談数が上がらないと考え、KSFは下記のように定義しました。
KSF=アポにつなげるためのフォローアップ体制・施策を確立
関連記事:KSFの設定方法と具体例|効果的なKGI・KPIとの連携術
5.目標の設定
ここで、目標の設定です。
売上=商談数×受注率×平均単価
売上目標は、2億円、平均単価が1,000万円です。(2億円=商談数×受注率×1,000万円)
一般的な受注率が20~30%という認識なので、目標は下記の通り。
2億=50×20%×1,000万円
6.運用性の確認
整合性
下記の2つのポイントを、確認します。
- KSFが変化すると、KGIも変化するか?
- KPIを達成するとKGIも達成するか?
実際にやってみないとわからないことも出てくるので、トライ&エラーで進めていくことも、スタートの段階で握っておくことが重要です。
安定性
KPIを管理するのに、負担がかかったり、データの収集が複雑だったりはしないか?など、管理面での安定性も重要です。MAやGA4のデータをLookerStudioなどで自動的に可視化できるような仕組みの構築も検討してみるのが良いかも。
単純性
単純で覚えやすいという視点も重要です。
7.悪化した場合の対策
対策は4つ
- さらに資金を投入
- さらに人を投入
- 両方や
- このままやる
悪化してから選択をするのは原始的なため、事前に4つのことを決めておきます。
決めておくこと4つ
- いつ
- どれくらい悪くなったら
- どうするのか
- 最終判断者はだれか
現在、立て直し中のため、1か月ごとに数字の確認はしますが、四半期単位で判断していきたいと思います。
四半期ごとに商談数を確認し、想定より〇%悪い場合は、インサイドセールス担当の対応工数増やす。
最終判断者は、営業部長。
8.コンセンサス
KPI・KGIそのものと、悪化した場合の対策に対する承認を得ておくことが重要です。
来週、コンセンサスをとってきます。
関連記事として、KPI設計に踏み切るための完全ガイド|設計・運用と失敗のポイント解説もまとめましたので、参考になれば幸いです。
本記事の参考書籍
最高の結果を出すKPIマネジメント
KPIの本質を理解し、業績向上を実現する具体的ノウハウを網羅。
この記事を書いた人[ABOUT]
WEBマスターやデジタルマーケティング業務で20年以上の経験。インバウンドマーケティングの仕組み構築と運用・グロースの責任者として、中小企業を中心に業務効率化をしてきました。
現在は、大手広告代理店グループで同様の任務を担っています。